INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国E45】 中国のホームページにおける正しい リニューアル方法
- 2【中国E46】 中国HP制作にデジタルマーケティングが必須になった現実
- 3【中国E43】 競合分析から見える中国回転寿司市場の勝ちパターン
- 4【中国E47】 中国で勝ち抜く日系企業のコンテンツマーケティング論
- 5【中国E49】 日系企業が生き残るためのホームページ制作 5つの新常識
- 6【中国E35】 DeepSeekに聞いてみた(中国情報技術 (IT) 業界)
- 7【中国E48】 日系企業が知るべき「コンテンツ覇権時代」の生存戦略
- 8【中国E41】 中国市場における 「半導体企業のポジショニング分析」
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国E48】 日系企業が知るべき「コンテンツ覇権時代」の生存戦略2025.02.16
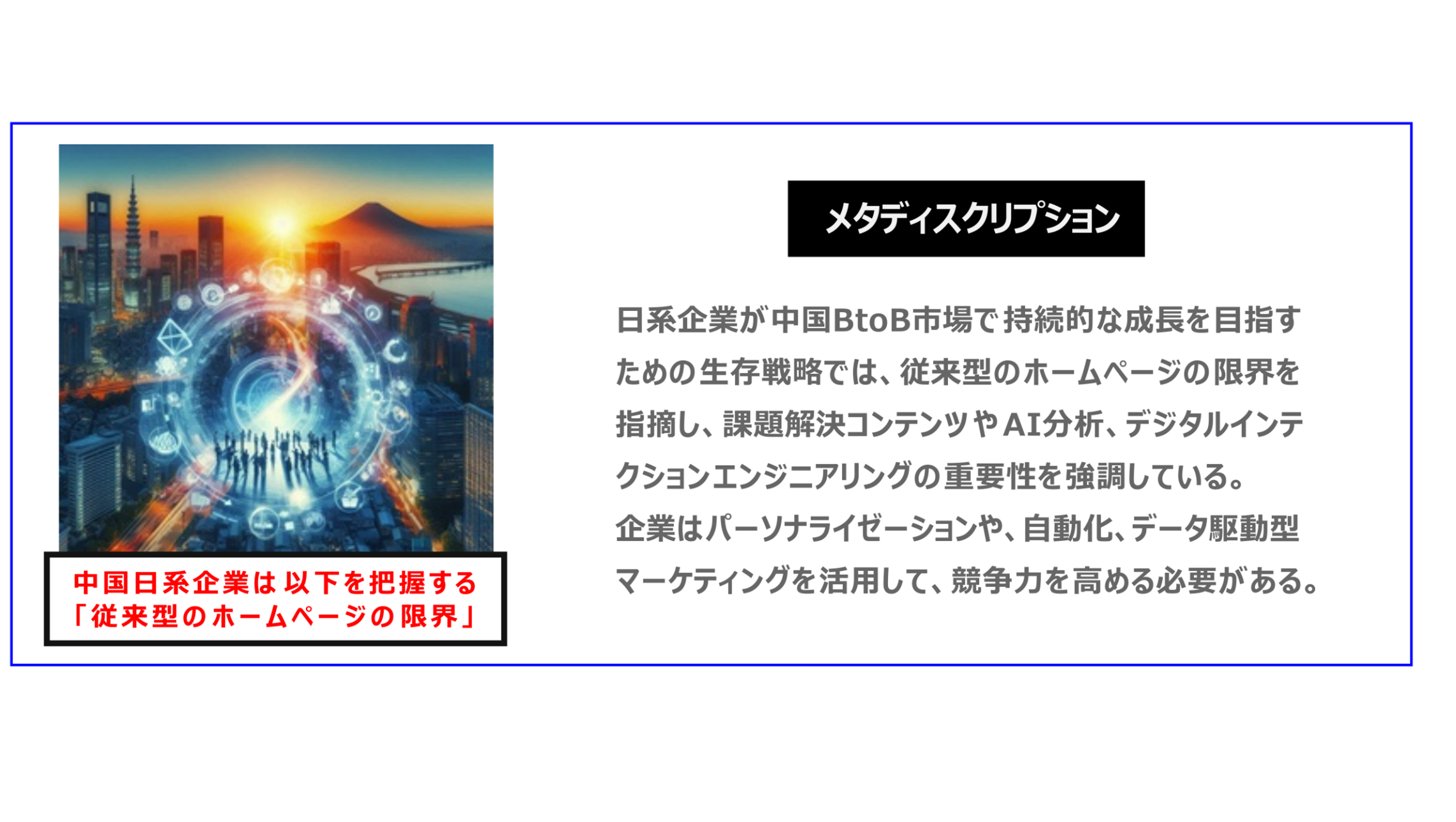
1. 従来型ホームページの限界
①中国日系企業が犯す「ホームページ自滅」の実態とは
2023年、北京で開催された日系企業マーケティング
フォーラムで明らかになった在庫管理システム A社
の事例は「デジタル時代の遭難事故」そのものだった。
↓
3億円の投資が月間 1,200PVという砂漠のような少な
い数字に消える背景には、中国BtoB市場の地殻変動
を見逃した「日本式ホームページ病」が潜んでいた。
②自己陶酔型コンテンツが顧客を殺す
A社の分析で明らかになったのは、20ページ中、
18ページが「会社概要」「品質方針」「沿革」などの
自己陶酔型コンテンツで占められていたことが判明。
↓
これは、中国BtoB市場で生き残れない
典型的な「日本式ホームページ病」の症例である。
③中国の購買担当者が真に求めるのは、
「この会社が何者か」ではなく、以下。
「我々の課題をどう解決するか」
④HSBCレポートが示す86%の企業が検索エンジン
で情報収集を開始する現実は、以下を告げている。
「従来の営業主導型ホームページモデルの終焉」
⑤蘇州の産業用ロボットメーカーB社が、9ヶ月で、
自然検索流入 17倍を達成した秘密は、まさにこの
「変化を先取りしたコンテンツ戦略」にある。
(例❷)蘇州で産業用ロボットを販売するB社の事例
①コンテンツマーケティングが生む
「見込み客の自動選別装置」
蘇州で産業用ロボットを販売する
B社の成功事例が参考になる。
②同社は、従来の製品カタログ型サイトを
改造し、以下のコンテンツ戦略を実施した。
・業界別課題解決ガイド(40事例)
・導入前チェックリスト(PDFダウンロード)
・比較動画シリーズ(自社製品vs競合)
↓
同社が作成した40事例に及ぶ業界別課題
解決ガイドは、単なる成功事例集を超えた
「デジタル技術営業マン」として機能する。
③特に、「食品工場 省人化 方法」といった
長尾キーワードで、検索結果のTOP表示を
獲得し、問い合わせの質が劇的に向上した。
④興味深いのは、ダウンロード資料の閲覧進捗を
AI分析し 「最適なアプローチタイミング」を営業
チームに通知するシステムを構築した点。
例えば、食品工場向け省人化ガイドでは、衛生基
準対応のノウハウから、電力消費量計算式までを
網羅し、競合他社のカタログを陳腐化させた。
↓
これらの施策により9ヶ月間で、
自然検索流入が 17倍に増加した。
2. AIが解き明かす「最適な接触タイミング」の神秘
①B社の真の革新はコンテンツそのものよりも、
「ダウンロード資料の閲覧進捗をAI分析する」
システムにある。
ある事例では、自動車部品メーカー担当者が
ダウンロードした「導入前チェックリスト」
の閲覧パターンを分析。
↓
特定の項目で30秒以上の滞留時間が検知された
翌日、営業チームがピンポイントで、技術質問
を投げかけた結果、3週間で契約成立に至った。
このシステムが可能にしたのは、
「顧客の思考プロセスへの同乗」。
②従来のMAツールが、把握できなかった「どの文
章で、眉間の皺が深まったか」までを可視化する
AI分析は、中国市場特有の「表面に現れない本音」
を捉える新たな手段となっている。
3.「動画比較」が生む意外な波及効果(蘇州モデルの衝撃)
B社がYouTubeと、Bilibiliで公開した比較動
画シリーズは、想定外の波及効果を生んだ。
ある動画で、競合製品の電力消費量を実測比較した
ところ、コメント欄が技術論争の場と化し、結果的
に検索エンジンの「関連動画」推薦で露出が急増。
↓
これがきっかけで、同社の技術ブログが業界関
係者の必須チェックサイトとなった事例がある。
4. デジタル砂漠を緑化する3つの水源
①中国市場で成功するホームページ再構築には、
3つの要素が不可欠になった。
【不可欠要素❶】課題解決コンテンツの生態系構築
単発の事例紹介ではなく、業界課題を多面的に
カバーするコンテンツネットワークが必要である。
【不可欠要素❷】行動データの畑作化
アクセス解析を超え、顧客の思考プロ
セスまで耕すデータ活用が求められる。
【不可欠要素❸】コンテンツと現実の共生
オンラインで蒔いた種をオフライン
で、収穫する仕組みが成否を分ける。
②蘇州B社が月間 300件の高品質な問い合わせを
獲得する背景には デジタルコンテンツと「現実
の商習慣を架橋する不断の試行錯誤」がある。
例えば、PDF資料ダウンロード時にユーザーに
要求する情報は、職種と予算規模だけに限定。
↓
これにより、表面的な名刺交換を超えた
「真のニーズ把握を実現している」。
③中国のデジタル砂漠で、枯渇したホームページを
再生するには、従来の「情報掲示板」の発想を捨て、
「課題解決エコシステム」へと変容させる必要がある。
それは単なるホームページのデザイン改修では
なく、以下を根本から問い直す作業になる。
「組織全体の中国市場との向き合い方」
5. 中国市場特有の「3層検索戦争」攻略法
①日本との決定的な違いは、中国市場が
以下の三重構造を持つ点にある。
・百度検索
・微信検索
・抖音検索
②上海のマーケティングコンサルタント李氏は、
「成功企業は、各プラットフォームで異なる
コンテンツ戦略を展開している」と指摘する。
(例❸)化学原料メーカーC社の事例
・百度:技術白書+学術論文風コンテンツ
・微信:業界ニュース解説+政策分析
・抖音:工場現場の改善動画+技術者インタビュー
この棲み分けにより、同社は検索経由の
リード獲得コストを従来比 68%削減した。
↓
特に、抖音の「#生産効率向上ハック」タグ動画
が若手技術者の間で話題となり、予期せぬ新規
顧客層を開拓した。
6. コンテンツSEOの盲点を突く「暗黙知の可視化」戦略
①多くの日系企業が見過ごす重要なポイントがある。
それは現場の暗黙知をデジタルコンテンツ化する
「DEEP MINING」の可能性である。
②日系精密機器メーカーのD社は中国現地スタッフの技
術ノートをAI解析し、以下のコンテンツを自動生成した。
・よくあるトラブル解決データベース
・部品選定シミュレーター
・メンテナンス時期予測ツール
↓
この「生きたナレッジ」提供により 同社ホームページ
の平均滞留時間が 8分22秒(業界平均の3.2倍)に達し、
自然リンクが 357サイトから発生した。
7. コンテンツ戦略の成否を分ける「5段階熱量管理」
①コンテンツマーケティング最大の落とし穴は、
アクセス数を追いかけるあまり、「質より量」に
走る点である。
②広州のデジタルエージェンシーが開発した
「購買熱量スコアリングモデル」が示唆に富む。
【訪問者のエンゲージメント指標】
・スクロール深度70%以下 → 冷めた状態
・PDFダウンロード → 関心あり
・動画75%再生 → 強い関心
・複数ページ往復 → 検討段階
・シミュレーター使用 → 購買直前
(例❹)ある計測機器メーカーはこのモデルを
導入し、熱量レベル4以上のリードに限定して
営業リソースを集中。
結果、商談成立率が従来の2.3倍に跳ね上がった。
↓
鍵は以下を機械学習で可視化した点にある。
「コンテンツ接触回数とコンバージョン確率の相関関係」
8. コンテンツ過飽和時代の次なる一手
①杭州のテックカンファレンスで、
披露されたある実験がヒントになる。
ARグラスを装着した工場責任者が、設備の不具合
箇所を見つめるや否や、即座に関連する技術資料
と、代替業者リストが視界に表示されるデモ。
②これは単なる未来予想図ではなく、百度が、近年
ローンチ予定の「空間検索」機能の実証実験である。
この技術が普及すれば、ホームページの概念そのも
のが「空間認識型ナレッジインフラ」へと進化する。
③重要なのは、コンテンツの価値が「検索される情報」
から「状況に応じて湧出する知恵」へと変容する点。
9. まとめ
①中国市場で持続的な成長を目指す日系企業に
とって、今まさにコンテンツマーケティングの
「本質的な転換点」が訪れています。
②単なる情報発信から、購買プロセス全体を再設計
する「デジタルインテクションエンジニアリング」へ。
デジタルインテクションエンジニアリングとは、単に情報を発信するだけ
でなく、購買者が商材を購入するまでの全てのプロセスをデジタル技術を
使って設計し、最適化すること。
③企業が、購買者とのインタラクション(相互作用)を
以下のデジタル技術を使って設計し、購買プロセス全体
を最適化することにより、購買者が商材を購入するまで
の体験をシームレスで効率的なものにする。
・パーソナライゼーション
・自動化とAI(市場分析)
・データ駆動型マーケティング
「この記事についてのご意見をお聞かせください」ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
