INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化
- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場
- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング
- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口
- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」
- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)
- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは
- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国B04】 人事担当必見!採用活動を成功へ導く施策のオウンドメディア2023.02.13
1. 人事担当者の採用に関する主な悩み
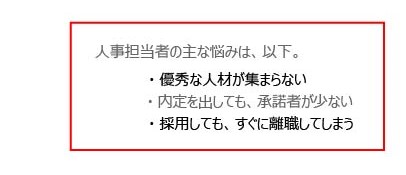
①このような課題には、共通する原因として以下がある。
「求職者ニーズに対して、企業の情報が伝わっていない」
②スマホが普及した現代では、日常の情報収集は、
必ずと言っていいほど Webが利用される。
Webで企業の情報を集める求職者にとって、以下のように思われると
離脱や他社に奪われる原因となる。
・どんな企業なのかわかりづらい
・どんな人が働いているかわかりづらい
・募集内容がわかりづらく、魅力的に感じない
↓
求職者はより深い情報をWebの中で探し求めている。
そこで重要視されているのが「採用オウンドメディア」
2. 日系企業が採用に苦戦する3つの理由
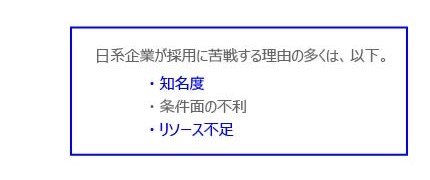
【理由❶】知名度で負けている
外部の求人サイトには多くの企業が求人を掲載している。
知名度の低い日系企業は、外部の求人サイト上で発見してもらう
ことが難しく、応募が集まりにくい現状がある。
※ 外部の求人サイトとは、51ジョブなどの求人会社が運営するサイトのこと
【理由❷】条件面で負けている
内定を複数獲得するような優秀な応募者の場合、以下の条件面は
入社を決める際の大きなポイントとなる。
・ 給与・福利厚生
・ キャリアップ
・ 教育・研修の充実度 など
条件を比較され、辞退となるケースは増えている。
【理由❸】採用ノウハウ・リソースで負けている
多くの採用担当者は他の業務を兼任し専任ではない場合が多い。
採用活動に十分な時間を割けていない現状がある。
採用にかける費用も潤沢ではない場合、限られた予算で採用活動
を行うには、さまざまな制約が発生し、ノウハウの蓄積も遅れる。
3. 優秀な人材を採用するために新たに対策すること
【対策❶】知名度への対策
①知名度不足は、以下の方法で補う。
・今までとは違う母集団形成の手法を導入する
・採用情報の発信方法を工夫する
②事業内容や仕事内容を箇条書きで数行程度、
サラッと書いてあるだけの求人募集が多く見受けられる。
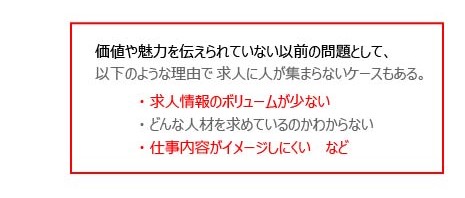
【対策❷】採用情報の発信方法を工夫する
外部の求人サイトの掲載内容や、自社のホームページを定期的に
メンテナンスすることが有効な対策となる。
以下の理由で応募されないこともあるため、クオリティと鮮度を保つ。
・ 内容が洗練されていない
・ 情報が古い
↓
採用ページをオウンドメディア化(動的ページ)することにより、
伝えきれない自社の文化や社風が伝わり、以下が期待できる。
「応募者に親近感を抱かせる効果」
【対策❸】条件面の対策
①給与や福利厚生などの条件面の不利を補う
以下の方法で自社の魅力を効果的にアピールし、入社意欲を
高めることで補っていく。
「入社後の姿を明確にイメージしてもらう」
②採用において、以下は多くの求職者が重視しているポイント。
「その企業で働くことで、自己成長が図れるか」
以下を明確にイメージできると入社意欲が高まる。
「入社後どのように成長し活躍しているのか」
↓
そのためには、以下の方法が有効となる。
・ 魅力的なロールモデルを設定する
・ 自社で活躍している社員を紹介する
【対策❹】企業の想いを伝える
他社と明確に差別化できる自社の魅力を訴求することも重要。
・ 自社のビジネスがどのように社会に貢献しているか
・ 社員がどのような想いで働いているのか
4. 採用オウンドメディアを作る理由
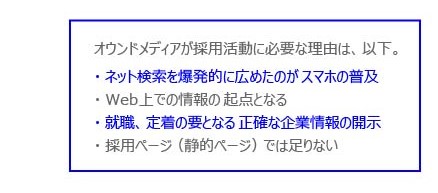
【理由❶】コロナの影響以外に以下の理由がある。
「Web広告効果(外部の求人サイト)の低下」
現在、知りたい情報はネットで検索するのは当たり前で、
ユーザーが気軽にアクセスできる情報量も爆発的に増えた。
①ネット検索を爆発的に広めたのがスマホの普及。
ユーザーの検索リテラシーが向上し、以下のユーザーが急増。
「自ら調べて検証し、情報を取りに行くスタイル」
②企業ホームページ内にある採用オウンドメディアにより、
誤報や誤解を避けて正確な情報を入手できるインフラができた。
ユーザーは企業からの情報をすぐに直接入手できるようになった。
【理由❷】 Web上での情報の起点となる
ほとんどの求職者は、スマホを使って情報収集を行なっており、
「スマホだけ」で完結する求職者も多いというのが昨今のトレンド。
求職者が情報を探したい時に、以下のようにスムーズに情報が
検索できないと、離脱される。
・ スマホの画面サイズに適していなく、見ずらい
・ サイトデザインが古く、欲しい情報がわかりづらい など
【理由❸】就職、定着の要となる正確な企業情報の開示
転職活動者が企業研究を行なう時の情報源として、
「企業ホームページを確認する」人が増えている。
↓
採用オウンドメディア上で詳細を見た上で検討する傾向がある。
①外部の求人サイトでは、企業一覧で多くの企業を知ることが
できるメリットがある一方で、以下のデメリットがある。
「情報は決まった枠組みで、情報が少ない」
②興味があり、もっと具体的に働いているイメージを持ちたいと、
思った企業については、ユーザーは以下の行動になる。
・ 外部の求人サイトではわからないリアルな情報を求める
・ 検索エンジンで企業名を調べ、企業について詳しく知る
そのため、採用オウンドメディアで訴求していく必要がある。
採用情報の発信には、以下が必須。
・ スマホに対応すること
・ オウンドメディアで行うこと
【理由❹】採用ページ(静的ページ)では足りない
①必ず見に来てもらいたいターゲットが欲しいと思う情報を載せる
さもないとターゲットがせっかく流入しても興味を無くし、離脱する。
↓
採用募集では、目的を整理してサイト構成を考える必要がある。
・ 誰に
・ どんな情報を届けるためのメディアなのか
②訴求ポイントは、以下のように「職場のリアル」がわかる情報
・ 職場の雰囲気
・ 業務スタイル
・ 先輩や上司の情報 など
③ホームページで発信している情報量が少ない企業ほど、
求人募集には自社の以下をしっかりと書き込む。
・ 魅力や仕事のアピールポイント
・ 求める人材
・ 待遇面でのメリット など
④他社と比べて独自の魅力的な要素があるにも関わらず、
魅力を抽出して言語化することができていないケースもある。
以下が採用オウンドメディアを作る上で必要となる。
「求職者が企業で働いているイメージをさせること」
5. 低コストで優秀人材を採用する新たな方法
①採用オウンドメディアに、事業内容や理念を積極的に発信する。
②若手社員や内定者に情報発信を任せる
若手社員や内定者の方が共感を呼ぶ情報発信ができるため、
彼らに運用を任せる。
以下のような情報を若手の視点で発信することで、自社の魅力が
十分に伝わりエントリー増に成果を出す。
・ 入社を決めた理由
・ 内定者から見た自社の魅力
③以下のようなコメントをよく聞く。
「うちの会社は、魅力的な要素なんてない。
BtoBで商材もわかりにくいし、知名度もないし、
福利厚生で特別なものがあるわけでもない」
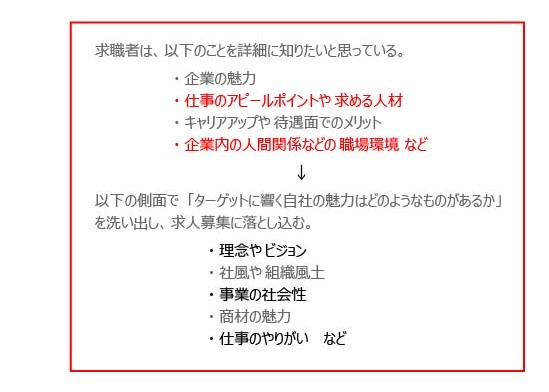
現在掲載している求人情報を見直し、
企業の魅力や募集内容をしっかりと伝えられる内容を再考する。
【注意】マーケティングなど周辺知識が必要になる
採用オウンドメディアは、採用マーケティングの要素が強い施策のため、
マーケティング知識が施策の成功失敗に影響する。
※ 弊社では採用オウンドメディアのコンサルティングを実施中。
・ 人材獲得に効果があるのか不安
・ どのように進行していけばいいのか分からない など
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
