INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化
- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場
- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング
- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口
- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」
- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)
- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは
- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国C12】 失注の理由は本当に価格なのか?失注の本当の理由は「不戦敗」2024.01.12
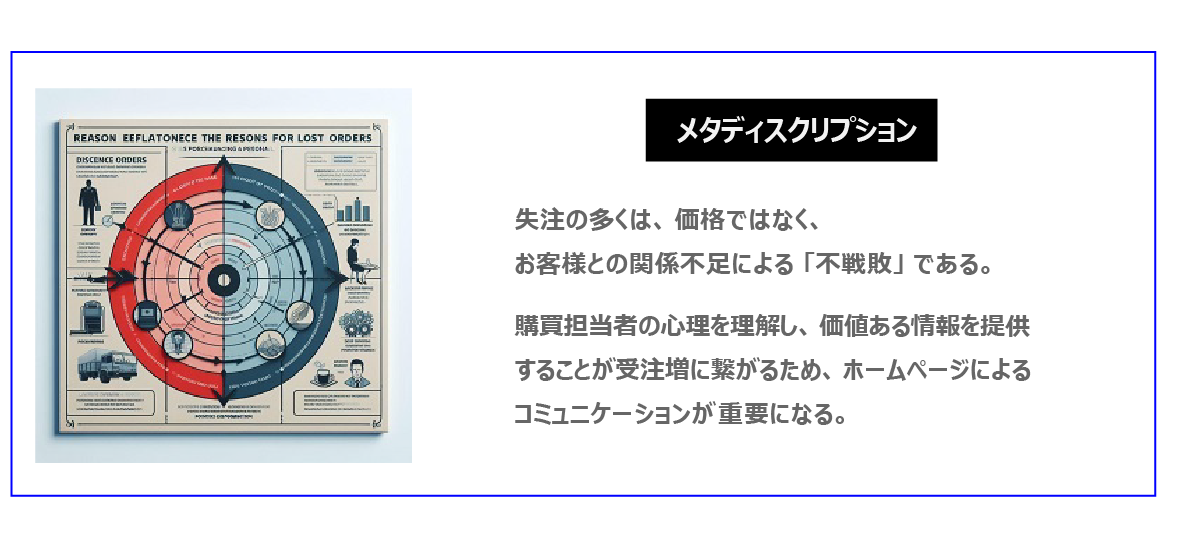
1. 失注の本当の理由
①あなたは営業マンとして、自社商材を売り込んでいるが、
なかなか受注につながらない(失注する)ことはないか。
あなたは商材に自信があるのに、
なぜかお客様からの反応が今ひとつなことはないか。
②失注の理由を聞いても、毎回同じような答えが返ってくる。
・価格が高い
・納期が遅い
・製品スペックが低い
③しかし実際には他社とそれほど遜色ないはずなのに、なぜなのか。
もしかしたら、あなたは知らず知らずのうちに、
お客様との距離を遠ざけているのかもしれない。
④今回はお客様との距離を近づけるために、以下のコツをお話する。
・選定する購買担当者の心理と行動を理解する
・お客様にとって価値のある情報を提供し続ける
これらのコツを実践すれば、あなたは不戦敗を防いで、
受注率を上げることが格段に高くなると思われる。
2. 失注の本当の理由とは、お客様との距離が近くなかったこと
①失注とは、一般的に商談したものの受注に至らなかったもののこと。
商談にならなかったものは対象外とする。
②失注の最も多い理由は、選定候補の2~3社として、
声がかからない状態、つまり「不戦敗」にあったと言える。
「不戦敗」とは、戦わずして負けることを意味する。
③これは営業の場合、お客様との関係構築や情報提供が不十分で、
選定の候補にすら入れない状態のことを指す。
つまり、見積もりすらされないこと。
不戦敗の原因は、お客様の心理や行動にある。
3. 選定する購買担当者の心理と行動
①BtoBビジネスの場合、何かを購入する際には、
選定する購買担当者という人が最も重要な決定権を持つ。
この購買担当者の心理と行動を掴むことができれば、
失注を防ぎ、受注を増やすことができる。
②選定する購買担当者の心理と行動には、以下の2つのポイントがある。
・2~3社から見積もりをとって選定するのが一般的
・直近の案件の有無によってアプローチの仕方が変わる
4.【心理と行動❶】2~3社から見積もりをとって選定するのが一般的
①BtoBビジネスの場合、何かを購入する際には、
2~3社から見積もりをとって選定するのが一般的。
これは、選定する購買担当者にとって、
忙しい業務の中で効率的に商品を選び、かつ相見積もりという
社内条件を満たすことができる最適な数字になるため。
②しかし、同じ商品を扱っている会社は2~3社でなく、
もっと多いはずだが、なぜ、2~3社に絞られるのか。
それは、選定する購買担当者が、
以下の2つの条件を満たす会社に声をかけるため。
・よく知っている会社
・直接コンタクトできている会社
③よく知っている会社とは、過去に取引したことがある会社や、
口コミなどで評判の良い会社など。
直接コンタクトできている会社とは、展示会やセミナーで
名刺交換した会社や、WeChatやメール、電話でやりとりした会社など。
↓
これらの会社は、購買担当者にとって、信頼できる会社というイメージがある。
また、商材の情報や内容などをすぐに確認できるという利便性がある。
④逆に、よく知らない会社や、直接コンタクトできない会社は、
購買担当者にとって、リスクが高い会社というイメージがある。
また、商材の情報や内容などを、
確認するのに時間や手間がかかるという不便さがある。
⑤つまり、購買担当者は自分の仕事を楽にするために、
効率良くするために、よく知っている会社や直接コンタクトできている
会社に声をかける傾向がある。
そして、その中から、価格や納期やスペックなどの条件で、
最適なものを選ぶ傾向がある。
このことから、最も多い失注の理由は、選定候補の2~3社として、
声がかからない状態、つまり「不戦敗」にあったと言える。
5.【心理と行動❷】直近の案件の有無によってアプローチの仕方が変わる
①選定する購買担当者に声をかけるには、
直近の案件の有無によってアプローチの仕方が変わる。
直近の案件とは、お客様が
今すぐにでも商品を購入したいと考えている状況のこと。
直近の案件がある場合とない場合では、
選定する購買担当者の心理や行動が異なってくる。
②直近の案件がある場合
直近の案件がある場合、購買担当者は以下の心理や行動がある。
・商材に対するニーズが高い
・商材に関する情報を積極的に収集する
・価格や納期やスペックなどの条件を重視する
・早く決断したいと思う
↓
この場合、購買担当者にアプローチするには以下が必要になる。
・商材のメリットや差別化ポイントを明確に伝えることで、
お客様に商材の価値を認識させることができる
・商材の情報や内容を簡潔に提示することで、
お客様に商材の内容を理解させることができる
・価格や納期やスペックなどの条件を柔軟に対応することで、
お客様に商材の選択肢としての魅力を高めることができる
・決断を促すためのインセンティブを提供することで、
お客様に商材の購入を決めさせることができる
③直近の案件がない場合
直近の案件がない場合、購買担当者には以下の心理や行動がある。
・商材に対するニーズが低い
・商材に関する情報を受動的に収集する
・価格や納期やスペックなどの条件にこだわらない
・決断を先延ばしにしたいと思う
↓
この場合、購買担当者にアプローチするには以下が必要になる。
・商材のニーズや問題を引き出すことで、
お客様に商材の必要性を認識させることができる
・商材の情報や内容を定期的に提供することで、
お客様に商材の関心を維持させることができる
・価格や納期やスペックなどの条件を優位に見せることで、
お客様に商材の選択肢としての魅力を高めることができる
・決断を後悔させないための信頼や安心を構築することで、
お客様に商材の購入を決めさせることができる
6. お客様にとって価値のある情報を提供し続ける方法
①選定する購買担当者との関係を継続的に深める方法とは、
お客様にとって価値のある情報を提供し続けること。
お客様にとって価値のある情報とは、以下のようなもの。
・商材の特徴やメリットを伝える情報
・商材の使い方や活用法を教える情報
・商材の導入事例や成功事例を紹介する情報
・商材に関連する業界の動向やトレンドを分析する情報
・商材に関連する問題や課題を解決する情報
↓
これらの情報を提供することで、お客様に以下の効果がある。
・商材に対する興味や関心を高める
・商材に対する信頼や満足度を高める
・商材に対するニーズや問題を認識させる
・商材に対する選択肢としての優位性を認識させる
・商材に対する決断を促す
②お客様にとって価値のある情報を提供し続ける方法として、
以下の2つの方法がある。
・WeChat公式ページやメルマガ、SNSなどで情報発信する
・自社ホームページのコンテンツ(お役立ち情報など)を充実させる
7.【方法❶】WeChat公式ページやメルマガ、SNSなどで情報発信する
①WeChat公式ページやメルマガ、SNSなどで情報発信する
ことで、以下のメリットがある。
・お客様とのコミュニケーションを維持できる
・お客様にとって価値のある情報を提供できる
・お客様の反応や興味を把握できる
②WeChat公式ページやメルマガ、SNSなどで情報発信する
には、以下に注意する必要がある。
・配信する頻度や内容を明確にすることで、
お客様に期待感や信頼感を持たせることができる
・配信する時間や曜日を工夫することで、
お客様の開封率やクリック率を高めることができる
・件名や本文を工夫することで、
お客様の興味や関心を引くことができる
・必ずCTA(コール・トゥ・アクション)を入れることで、
お客様に何か行動を促すことができる
8.【方法❷】自社ホームページのコンテンツ(お役立ち情報など)を充実させる
①自社ホームページのコンテンツを充実させることで、以下のメリットがある。
・お客様のアクセス数や滞在時間を増やせる
・お客様にとって価値のある情報を提供できる
・お客様の検索エンジンでの上位表示を狙える
・お客様の信頼や満足度を高める
②自社ホームページのコンテンツを充実させるには、以下に注意する必要がある。
・お客様のニーズや課題に応えるコンテンツを作ることで、
お客様に商材の必要性や価値を感じさせることができる
・コンテンツのタイトルや見出しを工夫することで、
お客様の興味や関心を引くことができる
・コンテンツの文章や画像を工夫することで、
お客様の理解や感情を高めることができる
・コンテンツには必ずCTAを入れることで、
お客様に何か行動を促すことができる
・コンテンツを継続して、更新することで、
お客様に最新の情報やトピックスを提供することができる
9. まとめ
①失注の本当の理由とは、お客様との距離が近くなかったこと
②選定する購買担当者の心理と行動とは、以下。
・2~3社から見積もりをとって選定すること
・直近の案件の有無によってアプローチの仕方が変わること
③コロナ禍で変化した企業の対応と対策とは、以下。
・知っている企業の商材を導入すること
・知名度が低いことによる「不戦敗」が起きていること
失注を防ぎ、受注を増やすためには、以下が重要。
「お客様にとって価値のある情報を提供し続けること」
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
