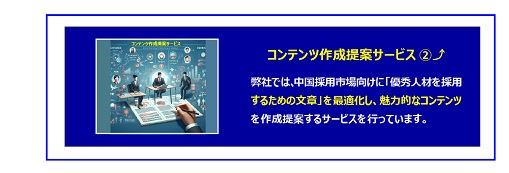INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化
- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場
- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング
- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口
- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」
- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)
- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは
- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国C74】 オウンドメディアが拓く未来 : 組織で創るオンラインプレゼンス2024.05.03
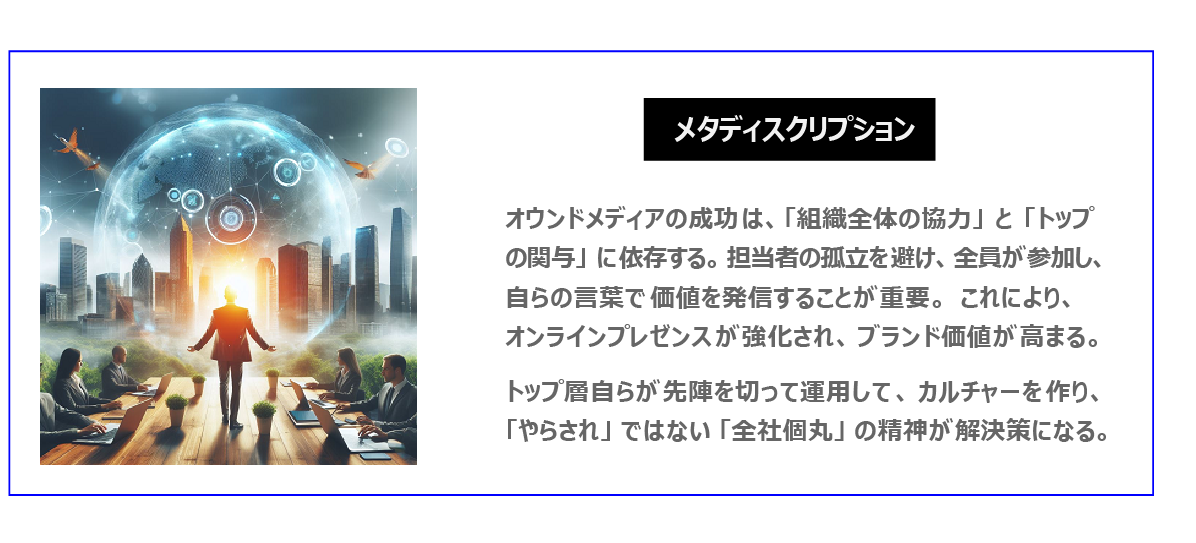
今回は、企業のSNS運用における新たなアプローチを提案し、
組織全体でのオンラインプレゼンス構築について、お話する。
1. 企業のSNS運用は、単なる情報発信の手段を超えた存在
①企業のSNS運用(オウンドメディアの運用)は、
企業文化の体現であり、ブランド価値を形作る重要なプロセス。
しかし、この重要なプロセスを担うSNS運用の担当者は、
「誰であるべきか」を問う。
②「えっ、それは担当者が運用していくに決まっている」と、
誰か一人が担当者として任命される。
トップは、その人を信じて託す。
↓
その「SNSの運用担当者」は、トップからの信頼に応えるべく、
「中の人」として積極的に発信していくことになる。
③例えば「企業ブランディングを強化しよう。
人事部でオウンドメディアを始めるように」と、
トップから言われ、人事部長がありがたく拝命する。
その部長も、特にSNSに詳しそうな若手を抜擢し、
「お前に任した。若い感性で頑張れ」と言いながら、
その平社員を信じて託すことにした。
このようなケースは少なくない。
④この場合、SNS(オウンドメディア)の運用は成功するか。
その担当者は孤軍奮闘することになりやすい。
「人事で運用担当を任された人のみが、ひたすら、
孤独に発信や運用をがんばる」という状況に陥りがちになる。
ひとりで頑張ることは、成果も、
それなりに上がるかもしれないが、とても辛い作業になる。
2. 特定の「担当者」が任命されることの問題点
SNS運用は、特定の「担当者」が任命され、その人が中心となって
運用されることが多いが、これには大きな問題が潜んでいる。
【問題点❶】担当者の孤立
①一人の担当者にSNS運用が委ねられると、
その人は孤軍奮闘し、やがて疲弊してしまう。
一人の担当者が全てを背負い込むことは、その人の疲弊を招くだけ
でなく、企業のオンラインプレゼンスの質を低下させる可能性がある。
②したがって、企業のオンラインプレゼンスは、
一人の力ではなく、組織全体の力で築かれるべき。
例えば、ある企業では、SNS運用を社内の様々な部門がローテーション
で担当することで、多様な視点と新鮮なコンテンツを提供し続けている。
これにより、以下が実現することになった。
・社員のモチベーション(やる気)の向上
・企業文化の積極的な発信
【問題点❷】トップ(総経理)の関与
①SNS運用の成功は、トップの関与に大きく依存する。
トップこそ、率先して発信するべき。
・SNSは苦手
・信用できない
・時代の風潮を見てしょうがなくやっている
そのように心の中で思っていたら、企業としてのSNS運用が成功するわけがない。
「運用者のことを気に掛けよう」とか、
「美味しいランチにでも連れていこう」とか、
「誰か一人でもその人のことを 気に掛けていれば、
当人は頑張れる」とか そういう次元の話でもない。
②トップ「自ら」が 「自分の言葉」でSNS(オウンドメディア)を発信する。
ここを人任せにした時点で「担当者を決めてその人にやらせりゃいい」
と 考えた時点でもう、 失敗への道筋が生まれてしまう。
「まずは何よりも、チーム全体で成功させようという、
会社トップの方針、そして 全体のカルチャーが最も重要なポイント」
↓
以下のような全体的な気運が生まれる。
「総経理や部長など上位役職者も、自ら積極的に情報発信する
ことにより、初めてみんなでやった方が良い」
③下の立場の方が孤軍奮闘しているケースが、
日系企業にはとても多いように感じる。
こういう場面が増えると、 担当者の心が折れ、実績も出ず、
会社のためではなく、個人のためだけに運用するようになる、
もしくは形だけ運用する、 ということが増えていく。
↓
トップ(総経理)が自らSNSを運用し、積極的に発信することで、
組織全体にその重要性が浸透し「全員が参加する気運」が高まる。
例えば、ある企業では、「総経理自ら」がコンテンツを執筆し、
企業のビジョンや業界の洞察を共有している。
結果、読者との信頼関係を築き、ブランドの認知度を高めている。
3. 企業のSNS運用は 企業の「顔」になる
①企業のSNS運用は、情報の共有だけでなく、
企業の「顔」としての役割も果たす。
理由は、企業の価値観、専門知識、
そして何よりも「人間性を伝える手段」になるため。
②SNS(オウンドメディア)は、顧客やパートナーとの関係を
深めるための対話の場であり、企業の内面的なブランディングを
強化するための重要なツールである。
4. SNS運用は組織全体の協力とトップの積極的な関与
結論として、SNS運用は、一人の担当者だけの仕事ではなく、
組織全体の協力とトップの積極的な関与によって支えられるべき。
理由は、SNS運用の成功は、
「トップの関与」と「組織全体の協力」によってのみ達成されるため。
↓
これにより、企業はオンラインでの強固なプレゼンスを築き、
ブランド価値を高めることができる。
結果として、企業の持続可能な成長に寄与することになる。
5. 特定の「担当者」が任命されることの解決策
【解決策❶】全社個丸の精神
SNS運用は、トップから最前線の社員まで、
全員が関与することで、初めて真の効果を発揮する。
↓
それぞれの個性を活かしながら、
一丸となって取り組む「全社個丸」の精神が必要になる。
【解決策❷】個性の尊重
それぞれの社員が自分の言葉でストーリーを語ることで、
オウンドメディアは読者に信頼され、ブランドの魅力が増す。
↓
強制された内容ではなく 「自発的な発信」が求められる。
6 企業におけるSNS運用のキーパーソンとは企業のトップ
①総経理「自らが」まず、SNS(オウンドメディア)の運用をすべき。
まずは、トップが実践する。
そして、部長など上位役職者も自ら積極的に発信を心がける。
↓
そうすることにより、初めて
「みんなでやった方がいいよね」という全体的な気運が生まれる。
②この気運により、会社全体の知名度やブランド力が向上し、
社外とのリレーションが強化される。
社外とのリレーションが強化されると、結果として、
SNS(オウンドメディア)経由での営業・マーケティングや、
人材採用がどんどん進むようになる。
↓
トップ層自らが先陣を切って運用してカルチャーを作り、
「やらされ」ではない「全社個丸」(それぞれの個性を活かしつつ
塊になって運用する)の企業が増えていくことをおすすめする。
7. 「全社一丸」ではなく、「全社個丸」
①チーム戦だけど、誰かがやればいい、ではない。
「やらされ感」あってもダメ。
「これこれこのように発信していくように」 と、
会社が業務命令として ある内容を発信することを強要した
ところで、 本質的には意味が無くなる。
②「それぞれが個性を活かして発信」しないと、
情報発信を受け取る読者には簡単に見破られてしまう。
読者の「SNSリテラシー」は、上昇してきているため、
以下のように感じさせてしまっては逆効果。
・この会社はやらせているんだな
・みんなで運用している風を装っているだけだな
③でも、やらせている内部ではわからない。
全社一丸となって頑張っているから。
つまり、「業務命令で仕方なく発信する」
社員の心の中が、わかっていない。
④トップがまず「自分のストーリー」を語る。
それを受けて部長などの上司陣も自然と「自分のストーリー」を語る。
さらにそれを受けて平社員たちが自然と「自分のストーリー」を語る。
8. まとめ
①オウンドメディアの運用は、単なるマーケティングツールではなく、
「企業の魂を映し出す鏡」です。
トップから社員一人ひとりまでが、自らの言葉で企業のストーリーを
語り、共感を呼ぶことで、オンラインプレゼンスは真に強化されます。
②このような「組織全体で創るオンラインプレゼンス」こそが、
オウンドメディアが拓く未来になります。
個々の社員が、自分の言葉で企業の価値を発信することが重要。
③このようなオウンドメディアの新しいアプローチは、企業の
内部ブランディングを強化し、社外との関係を深めることに寄与します。
また、読者のSNSリテラシーが高まる中で、
誠実で個性的なコミュニケーションがより一層重要になっています。
④オウンドメディアを通じて、企業の未来を拓くためには、
「組織全体での協力」 と 「個々の貢献」が不可欠です。
「自分なり」に「自分の言葉」で発信すること。
担当者に、任せっきりにしていませんか?
発信する内容を「強要」していませんか?
(上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです)
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり