INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>
- お役立ち情報
お役立ち情報
![]() 人気情報ランキング
人気情報ランキング
- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化
- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場
- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング
- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口
- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」
- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)
- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは
- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)
- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため
- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)
【中国E50】 景気減速の中での日系企業の戦略 (コスパ重視~先端技術)2025.02.23
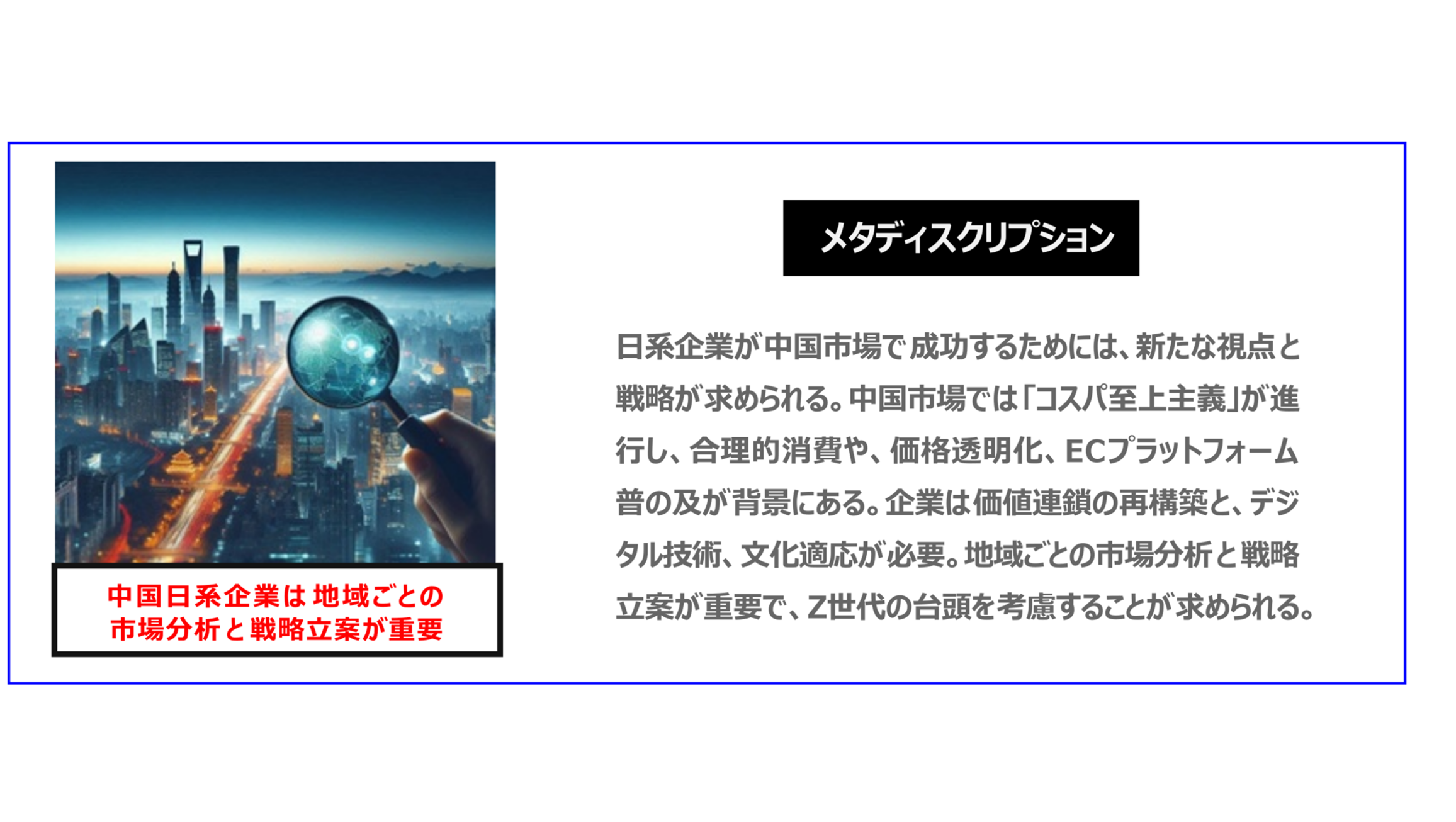
1. 中国市場は世界最大級の規模
①日系企業にとって、中国は、
「重要な市場であり続けている」。
しかし景気減速の中における中国戦略は、従来の
ビジネスモデルをそのまま適用するのではなく、
「新たな視点と新たな戦略」が必要になっている。
②今回は中国の新潮流トレンドと、中国日
系企業における戦略を分析したお話をする。
2.(中国ビジネスの新潮流❶)「コスパ覇権」の核心
①中国消費市場が「コスパ至上主義」に突き
進む背景には、3つの構造変化が存在する。
【構造変化❶】都市部中間層の拡大(約4億人)
による「合理的消費」の一般化。
【構造変化❷】Z世代(1995-2009年生まれ)の
台頭による「価格透明化」の加速。
【構造変化❸】ECプラットフォームの浸透が
もたらした「価格比較慣行」の定着。
②日系企業がこの潮流を掴むためには、単なる
値下げ競争ではなく、以下が求められる。
「価値連鎖全体の再構築」
③中国市場で「値ごろ感」が武器になる理由は、
中国の繁華街に佇むサイゼリヤの店舗を見れば
明らかである。
平日の昼下がり、多くの人で賑わう店内では、
9元(約185円)のペペロンチーノなど、1人で
何皿も発注し、談笑する若者たちの姿が目立つ。
↓
この光景は、単なる「安さ」を
超えた戦略的勝利の象徴である。
④サイゼリヤが描く「価値創造の四重螺旋」は、以下。
・農業直結型「サプライチェーン改革」
・生産工学を超える「調理の産業革命」
・心理戦略を織り込んだ「価格設定」
・都市圏別出店戦略の「巧妙さ」
(例❶)河北省の契約農場では、サイゼリヤが導入
する「クローズドループ農業システム」では、トマ
トの種子選定から収穫時期までを厳密に管理する。
(例❷)内蒙古自治区の専属牧場では、乳脂肪分
3.8%以上の生乳を安定調達するため、飼料配合
から搾乳時間までを規格化している。
これにより、主要食材の調達コストを同業他社比で、
23%削減(2023年調べ)することに成功している。
(例❸)広東省仏山市の中央厨房では、和風ドレ
ッシングの製造工程が秒単位で管理されている。
特筆すべきは「温度勾配理論」の応用。
↓
加熱工程で 0.5℃単位の温度制御を行うこと
で、素材の旨味成分を最大限に引き出しつつ、
エネルギーコストを 17%削減。
(例❹)上海の実験店舗では、AI画像認識に
よる調理時間管理システムを導入し、パスタ
の茹で時間を ±2秒以内に制御している。
⑤「9元戦略」の真髄は数字の魔術にある。
華東师范大学の消費者行動調査(2023年)によると、
中国消費者が「手頃」と感じる価格帯は、7元~12元
(飲食物)。
↓
サイゼリヤはメニューの 67%をこのゾーンに配置
しつつ、意図的に 14元の商品を散りばめることで
「相対的安さ」を演出した。
(例❺)成都の若者街・春熙路での出店
戦略は、地理的データ分析の傑作である。
半径500m圏内に大学生寮3棟(約8,000人)、
オフィスビル11棟(昼間人口 2.3万人)の立地
条件を活かし、テイクアウト専用窓口を設置。
(例❻)上海市では、地下鉄駅連結店舗の昼間
売上高が通常店舗の 2.3倍に達するなど、都市
インフラとのシナジーを徹底追求している。
⑥寿司チェーンのスシローが杭州市で展開する
「回転寿司2.0」モデルは、エンタテインメント
性と、コスパの融合事例として注目される。
デジタル体験価値の付加が客単価 15元台
でも、30%のリピート率を実現している。
↓
タッチパネル注文時に流れる寿司職人の実演動
画(平均視聴率82%)、QRコード読み取りで解
放されるゲームコンテンツなどがその例である。
※個人的には、デジタルスシロービジョン「デジロー」の大画面
による臨場感と、ネタのまぐろが美味しいのが気に入っています。
⑦ニトリの「3層価格破壊戦略」も興味深い事例。
・基本商品を現地メーカーと共同開発(コスト30%削減)
・中級ラインで日本デザインを採用
・高級品目では欧州ブランドと提携。
↓
この三角構造が、市場調査で以下の評価を獲得している。
「品質は日本並み、価格は国産品以下」
⑧重慶市で展開する無印良品の「長江モデル」
は、地域適応の好事例である。
以下の商品がその例である。
・湿度の高い気候に対応した竹素材家具
(収納力 +15%、価格 -20%)
・辛味調整可能な調味料シリーズ
(地元調味料メーカーと共同開発) など
⑨重要なのは「価格競争」ではなく「価値競争」。
中国商務省の調査(2024年)によると、
コスパ商品購入者の 78%が「品質保証」
を最優先条件に挙げている。
↓
日系企業にとって、以下を融合させるチャンスと言える。
・製造業で培ったプロセス管理技術
・中国のデジタルインフラ
⑩この潮流の先に見えるのは、単なる「安さ」
を超えた「スマート・コスパ」の時代である。
中国市場で持続的な勝者となるためには、
以下の三位一体戦略が不可欠である。
「サプライチェーン改革 × デジタル技術 × 文化適応」
3.(中国の著しい動き❷)「悦己」消費
①近年、中国では若者を中心に「自分のための消費」
という概念が急速に広がっている。
この潮流は「悦己(自分を喜ばせる)」という考え方に
基づいており、個性を重視した消費行動が特徴である。
(例❶)ローソンの成功事例:キャラクターコラボ商品で若年層を惹きつける
⑴ この「悦己」消費の潮流をうまく
活用している企業の一つがローソン。
ローソンは中国市場で「キャラクターとのコラボ
商品」を毎月展開し、販売を伸ばしている。
例えば、人気アニメや、ゲームのキャラクターを
起用した限定商品は若年層の強い支持を集めている。
⑵ これらの商品は、単なる食品や日用品ではなく、
消費者にとって「自分を喜ばせる」ためのアイテム
として認識されている。
特に若年層にとっては、キャラクターコラボ商品を
購入することが、自分自身を満足させるだけでなく、
「SNSを通じて自己表現をする手段」ともなっている。
②このような中国における消費行動は、
従来の「必要なものを買う」という消費スタイルから
「自分を喜ばせるために買う」という新しい消費スタ
イルへの変化を象徴している。
(例❷)長谷川香料の新工場計画:香料市場における「悦己」消費の影響
⑴ 長谷川香料は中国市場での需要の高まりを受けて、
2026年に、3つ目の工場を新設する計画を発表した。
↓
これは中国市場での「悦己」消費が、香料市場や、
フレグランス市場にも大きな影響を与えているこ
とを示している。
⑵ 特に個性を重視する若年層が「自分らしさを表現」
するために、香料を利用する傾向が強まっている。
例えば、特定の香りを選ぶことで、自分の個性や
気分を表現することができると考えられている。
↓
このような消費行動は、従来の「他人に好かれる
ための香り」から「自分が好きな香り」への変化
を反映している。
③長谷川香料は、この潮流を捉え、新たな商品開発
や、マーケティング戦略を展開することで、市場で
の競争力をさらに高めていくと予想される。
④「悦己」消費の広がりは、中国市場
全体に大きな変化をもたらしている。
従来の消費行動は、他人の目を気にしたり、社会的
なステータスを意識したりすることが主流だった。
↓
しかし、近年の若年層を中心とした消費行動は、自分
自身を満足させることを優先する傾向が強まっている。
⑤この変化は企業にとって新たなビジネスチャンスでもある。
消費者が「自分を喜ばせる」ために商品を選ぶように
なると、企業は、従来のマーケティング戦略を見直し、
個性や自己表現を重視した商品開発を行う必要がある。
↓
「悦己」消費の潮流は、今後も続いていくことが
予想され、企業は以下を正確に把握する必要がある。
「消費者が何を求めているのか」
4.(中国の著しい動き❸)先端技術の商用化
①中国はEV(電気自動車)や、自動運転、AI(人工
知能)などの先端技術の商用化が急速に進んでいる。
②日系企業も「これらの技術を活用し」、
中国市場での競争力を高めている。
トヨタなどの日系自動車メーカーは、
「中国のIT企業と協業し」、EVや自動
運転技術の開発を加速させている。
5. 中国市場の地域ごとに分析すること
①中国市場は景気減速が指摘されるものの、依然
として「巨大な市場としての存在感」を持っている。
②中国の名目GDPは、日本の4倍以上で
あり、経済規模の大きさは圧倒的である。
中国の中間層は4億人に達し、
消費市場としての潜在力は非常に大きい。
③2024年に日本を訪れた中国人の消費額は、
他の国々を大きく上回った(第1位)。
これは、中国の消費力が、
依然として高いことを示している。
④中国市場は、地域ごとに発展の度合いや、
景気の差が大きいため、一律に見るのではな
く「地域ごとに分析することが重要である」。
沿海部の大都市は、経済が発展している一方、
内陸部はまだ発展途上である。
↓
地域ごとの経済状況を把握することが必要。
⑤中国の地域ごとの変化は、非常に速いため、
最新の情報を常に把握し、戦略を調整することが必須。
今後、中国市場で成功するためには、
「地域ごとに市場分析し、戦略を立てることが重要」。
6. まとめ
①中国市場は、以下の多角的なアプローチが求められます。
・コスパ重視の戦略
・若年層をターゲットにした「悦己」消費
・先端技術の活用
②中国市場は、地域ごとに特性が
異なるため、以下が不可欠です。
・地域別の細かい市場分析
・地域別の的確な戦略立案
(参考)中国は地域ごとの特性に応じた産業クラスターの形成が進んでいる
「この記事についてのご意見をお聞かせください」
ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。
※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。
※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を
使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。
本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。
無断転載・複製は、固くお断りいたします。
以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり
